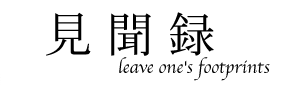 |
 |
2004.12 ラオス北部山岳地域のムラ 21日・22日・23日・24日・25日・26日・27日・28日・29日・30日・31日(1月1日) |
||||||
|
|
||||||||
| 2004年12月24日ウドムサイの朝は、霧の中にある。内陸の山間盆地なので毎朝この状態のようである、蕎麦を栽培すれば霧下蕎麦で思わぬ名産が生まれるかもしれない。 0700ホテルの食事はパスして、市場の片隅にある食堂で名物のカオ・ソーイ(辛い肉味噌米麺うどん)とラオ・カフェで朝食。市場で餅やミカンを買ってから出かけることにする。 |
||||||||
| 0800に霧のウドムサイを出発し、舗装された国道4号線を走ること1時間半、0940にホイチャイ村に到着した。この村は、クム族の村で鍛冶屋さんから聴き取り調査を行う。小屋がけされた鍛冶場には筒状の鞴、砂岩の歯口、爆弾を転用した鉄床、砂岩の砥石などが見られ、椀形滓や鍛造剥片なども観察できる。 鍛冶屋の調査後に集落を回ると、山の集落から降りてきたアカ族の人々に出会った。ガイドを通して話しかけたが相手方に会話の意志がなく。言葉もあまり通じなかった。 トレッキングツアーなどで案内される観光化された集落と違って、山岳地の普通の集落を巡っているためこのようなことは多いらしい。アカ族は精霊信仰が厚く、カメラを少し向けただけで顔色を変えて逃げていってしまう。撮影に成功したのは、すべて隠し撮りである。ホイチャイ村のクム族のおじさんの話では、彼らの脚で片道4時間のムラから薬草を売りに降りてきたとのこと、結構近いムラだと話していた。私たちの脚ではゆうに6時間はかかるだろう、残念だが調査は難しい。 ホイチャイ村を後にして、ウドムサイに戻る道筋で対岸にある廃村を見学。うち捨てられた高床住居の中や倉庫は、考古学的のも興味が尽きない。1230ムアンラーの塩泉で昼食。調査地には食事を取る場所がほとんどないため、朝ウドムサイのスパリーン食堂で弁当をもらって出発している。ラオスの山間で食べるお弁当も格別な味だ。 |
||||||||
| ムアンラーの塩泉は、あまり有名ではないが古くから塩の採取がなされてきた可能性がある。現在はルー族の人々によって塩田が作られ、鉄釜で製塩が行われている。 午後は、ルー族のおばさんから製塩作業に関する聴き取り調査を行った。最近、インドシナ半島の農耕文明の発展を握るキーワードとして「農耕・製鉄・製塩」が重要視されている。将来はこの丘から製塩遺跡が発見されるかもしれない。 |
||||||||
| 調査の後で対岸の温泉リゾートに立ち寄る。ウドムサイ県が経営しているらしく「地球の歩きかた」にも掲載されている。川岸には泥が堆積したプールのような施設があって、これが温泉施設だったようだ。現在は川沿いの岩場から沸く40度くらいの温水を洗面器で体にかけて入浴している。群馬の尻焼温泉に少し似ているが、ラオスの人々は湯の中に体を浸からす習慣がなく、温泉とは温水を体にかけることのようである。 夕方、ムアンラーを後にしてクム族が住むファイラー村に立ち寄ってからホテルに到着。夕食は、定番の餅米とラープ、作りたて厚揚げ入りのスープ、夜は冷え込むので市場でラオラオ(ラオスの焼酎)を購入して就寝。 |
||||||||