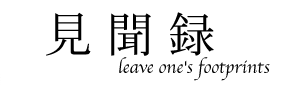 |
 |
2004.12 ラオス北部山岳地域のムラ 21日・22日・23日・24日・25日・26日・27日・28日・29日・30日・31日(1月1日) |
||||||
|
|
||||||||
| 2004年12月27日0600起床、今日は河岸を変えて市場の隅の中華食堂で朝食。肉まんを頬張ったあとで市場の食堂でラオ・カフェを飲み0800出発。今日は昨日案内を頼んだ村に立ち寄ってからラオリー村に徒歩で向かう。昨日の村に行くと村長さんが案内してくれることになり、すぐ出発。自動車が入れる道路から山を越え、谷を越え歩くこと1時間40分。そこにラオリー村があった。 | ||||||||
| ラオリー村は、今から50年前にはあったがそれ以前はわからないという、もしかしたら起源が古いかもしれない集落である。ラオス北部山岳地域の山の村は、少数民族が移動しながら生活することやインドシナ内戦などの政治的な影響で集落自体の成立年代は新しいものも多い。現在、25世帯193人が生活するモン族のムラである。 | ||||||||
| 昨日のヤオ村と同様に高床倉庫や平地式住居が見られ、鍛冶屋さんの聴き取り調査を行った。この村も焼畑を行い陸稲やトウモロコシを生産している。 | ||||||||
| 平地式住居の中ではお昼前だったが、冷えかかった鍋の麺を子供たちが手づかみで立ち食いの状態であった。復元された弥生住居の家族の食事風景と違って、生々しい。 | ||||||||
| 住居の中には干した豚肉(ベーコンだ)、ちまき、トウモロコシなどが乾されており、食生活も豊かな感じがする。一年をとうしてこの状態なのかは不明であり、モン族の正月に訪れたための光景かもしれない。 | ||||||||
| ムラの調査を終えて1300に下山。途中の尾根で案内役の村長にもランチを振る舞って昼食。下山しながらからラウリー村の昨年の焼畑跡をみる。4haぐらいの西南向きの斜面には、出ずくり小屋と思われる高床建物が二カ所にみられ、刈り取られた陸稲の株やキビの穂がみられた。高床建物の周りには脱穀済みの穂束がみられ、博物館の弥生時代の復元展示で示した稲束(たぶん唐古・鍵遺跡がモデルか?)とサイズやボリュームがそっくりなのでびっくり。 1600にはウドムサイに戻って丘の上から町の風景を撮影した。夕方は、ウドムサイの街をぶらり散歩し、インターネットカフェからからっ風96にアクセス。1830にスパリーン食堂で今回のウドムサイ滞在で最後の夕食。芥子の実と黒糖のつきたて餅がサービスで饗された。魚の酸っぱいスープに鶏のラープ、揚げ春巻きと餅米でお腹が膨れて眠くなった。ラオ・カフェを飲む神野夫妻を置いて一足先にホテルのベットへ。無事にウドムサイ周辺の調査を終えたことと満腹で一気に睡魔が・・・。 |
||||||||