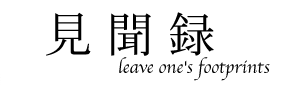 |
 |
2005.2 ラオス北部山岳地域の集落調査 その1 27日・28日・3月1日・2日・3日・4日・5日 |
|||||
|
|
|||||||
| 2005年3月4日、0630に起床。今日は調査最終日。ルアンナムターに向かう国道沿いの村を訪ね、帰りに初日に訪れたナンペー村の畑を見学する。朝0800に出発。途中、ポング村から分岐して未舗装の国道3号線出でると、熱帯雨林の森の中をタイと中国の援助で国道の拡張工事中。かなり大規模な自然破壊が進行しているが、ラオス経済のために納得。熱帯雨林の回復力に期待する。 |  |
||||||
| 道路工事の合間に広がるのは熱帯雨林の森、尾根を周りながら山道を登ると照葉樹の豊かな森が続く、まるで宮崎県の山の中を車で走っているような気分だ。とても雰囲気がよく似ている。0945ラミ族の集落であるナガム村に到着。長老のトンリーさんから焼畑の話を聞き取り調査。現在は焼畑と低地の水田耕作を主にし、焼畑の規模は少ないという。1975年に政府の政策で山から降りたが、以前は山に村があり、10〜15年休耕サイクルで焼畑のみを行っていたという。また、ラミ族は家ごとに精霊の祭壇はなく、村の集会所に祭壇がある。 |
|||||||
 |
|||||||
| 村の広場に大型の住居があり、これが村の集会所兼精霊の祭壇であるという。建物の入り口と内部に二カ所の精霊の祭りの祭祀具がある。遺跡でこれが出てきたら、やはり「神殿」といった呼び方になるのだろうか? | |||||||
| また村の中にある倉庫には、ネズミ返しの部分に精霊の祭りの祭祀具があり、倉庫に穀物が再び戻るための祈りの意味であるらしい。この村では、5月と9月に「業・(ぎょう)」と呼ばれる精霊の祭りを行い、祭りの間は、村人は村から出られず、また村外から人も入れない祭りを伝統としている。祭りでは鶏や豚が生け贄にされるという。山中で焼畑を生業としてきた伝統集落の祭りの中身は、どのようなものだろう? |  |
||||||
| ナガム村からポング村に戻り、川魚の唐揚げと魚のスープの昼食。午後はナンペー村に向かうが、この日は曇り空で日がささず、肌寒い。気温は20度前後だろか?昨日のこの時間は35度を超えていたから、熱帯の山岳気候は難しい。三日前に訪ねたナンペー村も快適な気温で、村人も活発だ。 |  |
||||||
| この日は、村長が不在だったので地区団長さんの家を訪ねると祈祷師の兄であるジュブーさんの家に通された。住居にはいるとそこは、精霊の祭りが今終わったばかりだという。祭祀具の状態を写真に撮り、祭祀の内容を尋ねると「次回の宝くじの当たり番号を精霊から聞き出していた」という。なんと祈祷師に憑依した精霊は、宝くじまでお見通しなのか?? |  |
||||||
| 地区団長のカワーさんの案内で村から2km離れた標高750〜800mの休耕地の見学と今年の焼畑及び伐採の聞き取り調査を行った。カワーさんの家では5箇所の畑を割り当てられ、4年休耕のサイクルで焼畑を営んでいる。この畑の調査を今年度行うことを約束し、村に戻る。 |  |
||||||
| 地区団長のカワー(45)さんの家族と甥。11人家族で長女は嫁に行き、長男はトゥーソン(23)五女のナニー(6ヶ月)の大家族だ。奥さん(35)は再婚だという。この家族とも再会を約束して村から戻る。 |  |
||||||
| 調査最終日の夕飯は、運転手とガイドを招いての宴会。メコン川沿いのフェイサイレストランで運転手自慢の川魚のしゃぶしゃぶ。鯉の身に似ていて癖がない白身で美味しかったです。当地としては高級のフランスワインを二本もあけて三人ともご満悦。次回の調査はいつの日か?運転手のノさんは、中古車販売から三菱の4WDを購入して運転手兼ガイドに転身。将来は竹製品の事業を行いたいとのこと。ガイドのパイワン氏も奥さんにパソコンショップを任せ、実業家を目指している。ほど良く酔って、未来を語らい、ラオスの将来を語らい再会を誓いました。 |  |
||||||