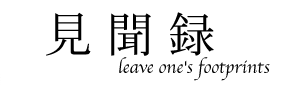 |
 |
||||||
| 2005.2 ラオス北部山岳地域の集落調査 その1 27日・28日・3月1日・2日・3日・4日・5日 |
|||||||
|
|
|||||||
| 2005年3月1日、0530に起床。宿泊したホテルは「タービシン・ホテル」、フェイサイの街で最もホテルらしいと呼ばれているので宿泊したが、ウドムサイのそれとさほど変わりなし、1泊400B(1120円)。 ルアンパバーンの托鉢を思い出し、朝早く起きたが?フェイサイの托鉢は、朝0640頃からはじまる。 |
 |
||||||
| ルアンパバーンのそれに比べれば、規模はとても小さいが、それでも早朝のラオスの風物詩だ。朝食は、街のsousada食堂で麺を食べ、同席のフランス人からビデオを見せてもらった。 今日は、調査の初日で、ガイドのパイワンさんとフェイサイトラベルのガイド兼運転手のノさんとともに、三菱の4WDトラックで0800に出発。街から自動車で1時間ほど移動して、標高740mにあるモン族の集落である、ナンペー村に向かう。昼食は、チャーハンなどを弁当にして持参。 |
 |
||||||
| ナンペー村では、政府の人口調査が行われており、村の人が小学校に集まっていた。村長のラオワーコンさんから村の由来や焼畑のくらしの話を聞く。村は132世帯、800人以上が住む大集落で、1941年に7世帯が移住してから大きくなったようだ。 村の人々はモン族の衣装を身にまとっており伝統的な雰囲気が濃厚だが、自家発電機や精米機など近代機器も取り入れている。6月の祭りの日取りの情報を尋ねたら、日が決まったら携帯電話でガイドに連絡してくれると聞いてびっくりした。 |
 |
||||||
| 村を降りながらナンペー村の焼畑休閑地を見る、ここでは3〜4年の休耕サイクルで焼畑を行っている。ナンペー村は、フェイサイにも近く焼畑のほか果樹栽培も行っており、近郊農業に転換しつつある農耕集落だ。でも、標高の高い不便な場所にこだわる伝統的な気風の村でもある。村から降りる途中で麓のクム族の村人の焼畑のための伐採を見ることができた。 |
 |
||||||
| クム族の焼畑のための伐採は、休閑地の篠竹の伐採を行っていた。5人の家族と見られるチームで列を作りながら斜面を上がっていく。 |
 |
||||||
| これも北部ラオスによく見られる鉄鎌で伐採を行っている。村の鍛冶屋で生産された鎌であまり地域差がない。調査の最終日にナンペー村を再来することにしてナゴ川沿いのパング村の食堂で昼食、持参した弁当にスープを注文。 食事後にホテルへ戻って1500。気温は30度を越えており、冬に慣れた体が気温に慣れるまで少しつらい。この日は、ホテルで休息し夕方にフェイサイの町歩きでおしまい。暑季の調査は、こんな日程で体力の消耗を避けながら進めることにする。夕方に街の総菜屋台でカオニャオ(蒸した餅米)とソーセージ、野菜の総菜をテイクアウトして夕食。 |
 |
||||||