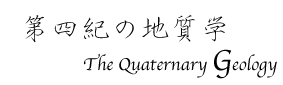 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
|
5. 議論 (1)高崎泥流堆積物の異なる二つの堆積面について 高崎泥流堆積物は高崎台地と井野川低地に分布し、その頂面高度の差は5m以上に及ぶ。早田(1990)は井野川低地の平坦面を井野川泥流堆積物の堆積面として捉えた。吉田(2004a,b)は井野川低地を榛名火山起源の水系によって開析された井野川泥流浸食面の井野面として捉えたが、竹本(2008a)は、井野面に地形全体を削剥した堆積物が見られないことから、浸食面である可能性を否定した。吉田(2008)は、竹本(2008a)の批判に答え�「井野川泥流浸食面は言い過ぎた感がある�」としながらも、小河川による削剥の可能性を述べた。 高崎市立岩鼻小学校南の粕川沿いの河川改修工事現場では、かつて厚さ数mの砂礫層を観察した。これは粕川が井野川低地に流れて堆積したものあり、その規模からも井野川低地を面的に浸食したとは考えにくい。また、井野川低地の発掘調査でも高崎泥流堆積物を浸食した堆積物を確認された事例を知らない。井野川低地の地形面は、高崎泥流堆積物の堆積面であると考えることが妥当であると思われる。 安中市の古屋遺跡群周辺の九十九川流域でも同じ現象がみられ、その標高差は10m以上に達する。このことから高崎泥流堆積物の堆積・運搬様式には流速の異なる二つの流れが存在した可能性がある。 高崎台地の各地で観察される高崎泥流堆積物は、軽石粒と火山灰基質に富む軽石流によく似た層相と河川礫を多く含み、砂層などを挟在して成層した層相が観察できる。 高い頂面高度を呈する堆積物は、最初に比較的高速の流れによって谷からオーバーフローして平坦な堆積面を形成した。その後に堆積物の速度が低下して谷に低い頂面高度を持った堆積面を形成した。つまり水を含まない岩なだれのような泥流堆積物と流水の影響を受けた二つの堆積物が存在したかもしれない。 また、時代の異なる泥流堆積物が高崎台地と井野川低地に堆積した可能性も全くないわけではない。現在までにこれを示すような観察は得られていないが、その可能性も全く否定できるものでないことを指摘したい。 (2)晩氷期に集中する山くずれ堆積物について 晩氷期と呼ばれる15.0から11.5千年前は、寒冷気候から温暖気候に移行する時期として最古・古・新ドリアスと呼ばれる寒冷期を経て温暖化が進んだが、この変化は広域かつ劇的な気候変動だった。 浅間板鼻黄色テフラから浅間総社テフラの間は、利根川扇状地の周辺で急激な森林植生の変化が起こり、温暖化が進んだと考えられている(辻ほか1985)。この層位には、利根川扇状地の周辺で高崎泥流堆積物や行幸田岩なだれ堆積物、徳丸ラハール堆積物などが見られ、赤城山麓でも白井泥流堆積物(竹本2008b)がみられるという。各地の堆積物は限定された分布であることやテフラを伴わないことから、それぞれの堆積物の層序関係は不明である。また考古遺物との層序関係は、徳丸ラハール堆積物や行幸田岩なだれ堆積物でみられるが、遺物の上限年代が示されているに過ぎない。 この時期は浅間火山の板鼻黄色テフラや平原火砕流堆積物によって群馬県西部では大規模な植生破壊が起こっているだろう。火山活動や地震、急激な気候変化といった別々の要因でそれぞれの堆積物が形成された可能性は高い。 しかし一方で、高崎泥流堆積物の分布を群馬県西部で起こった地震に求める考え方(大塚ほか1997)、(高浜・大塚2001)やそれを支持する中村(2003)や竹本(2008a,b)など。また高崎泥流堆積物を浅間火山の第二軽石流堆積物との関連を示唆する考え方(早田2000b)、(早田2003)もある。なお、早川(2010)は浅間火山の軽石流期における第2軽石流は、平原火砕流堆積物のラハール堆積物と考えており、この成因も含め一連の火砕堆積物の層序対比を今後は検討する必要がある。 (3)榛名山麓と赤城山麓に見られる総社砂層相当層について 群馬県中央部の第四紀編年において始めて詳細な完新統の編年を行ったのは早田(1990)である。赤城南面から大間々扇状地、前橋台地にかけて完新世段丘の開始期を鬼界アカホヤテフラ降下前の縄文時代早期末に求め、縄文時代中期末に段丘化が起こったことを明らかにした。また前橋台地縁に分布する扇状地末端の砂質堆積物に注目し、総社砂層と呼んで関連する堆積物を検討した(早田2003)。この間に進んだ前橋台地周辺の発掘調査、例えば前橋市の熊野堂遺跡(前橋市埋蔵文化財発掘調査団1988)や飯土井二本松遺跡(事業団1991)などの調査成果は、総社砂層に関する多くの情報を提供し、また各地の遺跡調査は沢山の放射性炭素年代を供給した。 現在の視点でみれば総社砂層及びその相当層は早田(2003)が注目したように利根川扇状地に広域に分布していることがわかる。また、それらの堆積物の堆積開始期は、ほぼ一様であり浅間宮前テフラの降下期で縄文時代早期撚糸文期末の10.5千年前である。 この時期は、波志江中屋敷東遺跡の花粉分析によって、亜高山帯針葉樹林が消滅しナラ林が成立した時期(古環境研究所2002)に当たり後氷期の急激な気候温暖化が起きた時期(ボレアル−アトランティック期)である。かつて辻ほか(1985)は、前橋泥炭層の浅間板鼻黄色テフラを境にして、前橋台地周辺では亜高山帯針葉樹林が衰退しコナラ亜属が急増すると同時にブナやスギ属の増加が見られ、気候の急激な温暖化と湿潤化が進んだとした。この時期は14.5千年前にあたり、すでに前橋台地周辺の急激な温暖化はこの頃からはじまっていた。 尾瀬ヶ原では、泥炭層の基底が放射性炭素年代で8千年前に遡ることが明らかである(阪口1989)。この頃から脊梁地域では、冬期の多雪化が始まったと思われる。またこの時期に対馬海流の日本海への本格的な流入や黒潮の流入が進んだ(松島1984)。 このことから総社砂層の形成要因となった気候の温暖化は、冬期の多雪化や太平洋岸の湿潤化による降水量の急激な増加だったのではないだろうか。降水量の増加で河川の浸食・運搬作用が活発になると考えればこの地域の気候変化と火山コントロール性地形発達の差が説明できる。 最終氷期の最寒冷期にあたる20.0千年前に榛名火山の相馬山が噴火し、岩なだれ堆積物により山麓に大規模な植生破壊が起きた。岩なだれ堆積物を供給源にして山麓からラハール堆積物が広がるが、16.5千年前の浅間板鼻黄色テフラ降下時には、扇状地が形成され、離水して台地には森林の形成を伴って火山灰土が堆積した。 しかし、岩なだれの泥流丘やその周囲の相馬ヶ原扇状地は、ほとんど植生が回復せず裸地化していた可能性が高い。その理由は、陣場岩なだれ堆積物の流れ山に分布する上部ローム層の堆積状況が悪いことや榛名山東麓で縄文時代前期までの黒色土が一様に薄いことなどが挙げられる。相馬ヶ原扇状地は、後氷期まで浸食作用が卓越した場所であった可能性が指摘される。 こうした植生環境で10.5千年前から降水量が急激に増加し、相馬ヶ原扇状地内の小河川の下刻と土砂の運搬により山麓縁には総社砂層による新たな扇状地が形成された。降水量の変化は、増減を繰り返しながら5.0千年前頃まで続いた。この頃に相馬ヶ原扇状地にも黒色土が堆積し、前橋台地でも黒色土が堆積した。縄文時代中期以降に、広い範囲で森林を伴う植生環境に変化したのだろう。 同じ現象は赤城山麓でも起きたが、榛名山麓に比べて形成された扇状地の規模は極めて小さかった。赤城山麓の総社砂層に相当する堆積物は、一様に白色や灰色砂質堆積物で角閃石や軽石を含んでいる。これは、赤城火山の総社砂層に相当する堆積物の供給源が80千年前に赤城南麓に堆積した大胡火砕流堆積物であり、その起源が大胡火砕流の堆積面が浸食した谷であったからだろう。 赤城火山では最終氷期に火山活動が26から20千年前頃に山頂カルデラ内で起こった。これは赤城小沼や赤城血の池火口(早川1995b)の噴火であるが、山麓の植生を破壊する規模のものではなかった。最終氷期に形成された赤城南麓の白川扇状地は、28千年前の姶良Tnテフラ降下後に離水して火山灰土を堆積した。後氷期の降水量の変化によって新たに地形が浸食された範囲は、山麓が森林によって保護されていたので限定された場所になった可能性が高い。 この二つの火山山麓での後氷期の扇状地形成の違いは、その供給地が最終氷期に火山活動で植生破壊が起こったかどうかの違いなのだろう。 また晩氷期にかけて平原火砕流堆積物による大規模な植生破壊が進んだ浅間火山山麓は、平原火砕流の浸食が認められるが、完新世における規模の大きな扇状地は形成されなかった。これは、この時期に大きな噴火がなかった草津白根火山も同様である。 浅間火山や草津白根火山の山麓では高原にクロボクと呼ばれる黒色土が堆積している。クロボク土の成因はササなどの植生によるものだ。この地域は後氷期の降水量の増加に対しネザサの植生に覆われて、裸地化や浸食が進まなかったのではないだろうか。利根川扇状地周辺は、後氷期における冬期の多雪化の開始とともに冬から春先の季節風が卓越する地域にも変化した。冬場の凍上作用による火山灰土壌が、春先の強い季節風で移動し、容易に植生の回復が妨げたこともこの地の気候特性であるかも知れない。 こうしてみると火山コントロール性地形発達をもたらすイベントは氷期と間氷期のどこで起こるかによって、それがもたらす土砂の供給源が決定され、結果として火山麓扇状地の発達の差になるのかも知れない。矢口(1999a)は群馬県北部に分布する中期更新世の火山灰土と榛名火山山麓扇状地の関係を明らかにし、北西山麓の火山麓扇状地がステージ13及び11に急激に形成されたと考えた。群馬の裾野が広がる火山の風景は、東アジアのモンスーンに関係した、まさに風土が造ったものだろうか。 (4)榛名山南麓における縄文時代の遺跡と総社砂層 前橋台地周辺の植生変化は花粉分析により明らかにされた。しかし、花粉分析では降水量の詳細な復元は困難だ。内陸の閉塞湖では、湖水準の変動が堆積物に記録されていれば、降水量変動を知ることができる。 斎藤ほか(1999)は、諏訪湖底コアから過去9,500年間に7回の湖面沈降を伴う断層活動を認めた。この活動によらない湖水変動は降水量の変化に伴うものだと考えられた(福澤2006)。 諏訪湖の湖水準変動を降水量の変化と捉えると総社砂層及び関連堆積物の堆積期は、概ね湖面の上昇期すなわち降水量の増加期に一致する。 それは10.5千年前の浅間宮前テフラの降下期で縄文時代早期撚糸文系稲荷台式土器の時期。7.5千年前の縄文時代早期末の条痕文系土器の終末期。6.5千年前の縄文時代前期前半の黒浜式土器の時期。5.5千年前の縄文時代中期前半の勝坂式土器の時期。そして4.0千年前に埋積谷の下刻が一様に始まる縄文時代後期前半の堀之内式土器の時期である。これらの時期を見るとおよそ1.5から1.0千年周期で降水量が増加し、堆積物が山麓から供給された可能性が見て取れる。 こうした降水量変動は、冬季積雪や夏季の梅雨や台風等の活動を反映していると考えられ、1.5千年周期はBond cycleと呼ばれ、北大西洋でジェラード・ボンドにより発見された(Bondほか1997)。後氷期における気候変動の源は西部大西洋暖水域と東アジア夏季モンスーンがもたらす湿潤気候システムであると考えられ(福澤2003)、こうした汎地球的な気候変動が火山噴火によってコントロールされた地形環境に作用して完新世の扇状地形成や遺跡の立地や形成に深く関与しているのだろう。 かつて遺跡の立地と諏訪湖の水位変動に始めて注目したのは藤森(1965)であった。藤森が述べた諏訪湖盆遺跡の垂直分布図からは地震や降水量の変化により変動した湖水準と遺跡分布の変化が読み取れる。 ところで榛名山東南麓は、縄文時代の遺跡動態が調べられた地域である(鬼形1988)。これによると縄文時代早期に低調だった遺跡数は、前期の黒浜期に急増し諸磯B期に減少する。中期初頭の勝坂期はさらに減少するが、加曽利E期に急増し、縄文時代後期には減少に転じている。これを年代にしてみると遺跡の急増期は6.5から6.0千年前の温暖期である縄文時代前期前半、5.0から4.5千年前の中期後半である。この時期は降水量の減少期で、おそらく山麓から供給される土砂量が減少し、縄文人が住まう森林が安定した時期なのだろう。 これと同様の傾向は南関東地域の海浜地域でも認められる(松田2010)。縄文時代早期前半の撚糸文系土器期の11.5から11.0千年前はプレボレアル期にあたる。温暖化が進み降水量は減少して森林が安定したのだろう。遺跡数は増加するが、早期中葉の沈線文系土器の時期である10.5から9.0千年前に降水量が増加すると遺跡数が減少した。早期後半の条痕文系土器の時期である8.5から7.5千年前はボレアルからアトランティック期に移行し、降水量は減少して森林が安定したのだろう。これにより遺跡数は増加するが、早期末の7.5千年前には、再び降水量が増え、外来からの土器の移動が増えるなど外的な要因もあって遺跡数は減少した。 前期前半の時期である7.0から6.5千年前は縄文時代最温暖期で降水量も増えた。海浜地域では海進が進み、漁労活動が活発となり遺跡数が増加した。前期後半の時期の6.0から5.5千年前には降水量が減り、海退期に転じて海浜地域の遺跡数は減少した。前期末に続いて中期初頭の5.5から5.0千年前には降水量が増加し、森林が安定しないので遺跡数が増えなかった。しかし、中期後半の時期の5.0から4.5千年前には降水量も減り、大規模な環状集落が出現することにより遺跡数は増加した。中期末の4.5千年前には急激な気候の悪化があり環状集落は崩壊して遺跡数が減った。 こうしてみると気候の温暖化のみならず、降水量の変化と遺跡数の傾向はよく調和していることに気づく。これは当時の集落維持の要因が海浜地域や内陸河川の漁労及び山地の森林から得られる採集食糧資源に依存していることが遺跡数増減の理由である。そのために降水量を指標とした気候変化と遺跡数の変化に調和的な相関がもたらされているものと解釈できる。吉川(1999)は関東平野の12,000年間にわたる植生史を明らかにした。今後は関東平野の地域ごとの詳細な植生復元と遺跡群の変化を明らかにすることが遺跡立地を語る議論の要だろう。 謝辞 高崎市立中尾中学校の新井雅之さんには、長年の共同研究でお世話になりました。群馬大の早川由紀夫さんと日本大の竹本弘幸さんには日頃からご助言をいただきました。当事業団の岩崎泰一さんからは、執筆の契機をいただきました。藤巻幸男さん、洞口正史さん、右島和夫さん、大西雅広さん、大木紳一郎さん、南雲芳昭さん、石坂茂さん、井川達雄さん、友廣哲也さんからは仕事を通じて考古学の考え方を学びました。飯島静夫さん、麻生敏隆さんからは文献をいただきました。安中市教育委員会の千田茂雄さん、壁伸明さんからは遺跡の情報を教えてもらいました。また、中村正芳さん、地学団体研究会、野尻湖発掘調査団、第四紀総合研究会、高崎地学愛好会の皆さんには、過去に言葉に尽くせないほどお世話になりました。以上の方々に厚く御礼申し上げます。 |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||