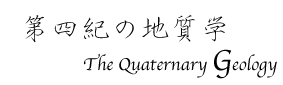 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
|
(2)前橋台地とその周辺 |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||
(2)前橋台地とその周辺
カラー
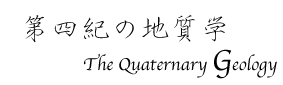
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題
矢口裕之
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月
研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂
高 崎市の新保田中村前遺跡(事業団1993)は、染谷川沿いの前橋台地II面に位置している。遺跡の地下には下位より前橋岩なだれ堆積物、黒泥、元総社ラハール堆積物が見られ、黒泥から4,120±110y.BPの放射性炭素年代を得られた。1993年に行われた発掘調査でこの層序を直接確認した。元総社ラハール堆積物は、染谷川の自然堤防を形成し、元総社ラハール堆積物の上位には埋没谷を埋めた砂層や黒泥などの堆積物がみられ、3,030±80y.BPから2,090±90y.BPの放射性炭素年代が得られた。
このことは自然堤防形成を伴った前橋台地II面は50千年前に形成され、それ以降に河川の河刻により谷が形成され縄文時代後期から晩期にかけて谷の埋積が進んだものと思われる。
高崎市の菅谷石塚遺跡(事業団2003)は、井野川と染谷川の中間にある前橋台地II面に位置している。遺跡では陣場岩なだれ堆積物が認められ、その上位に浅間大窪沢1、2、浅間板鼻黄色テフラが検出された。この遺跡では陣場岩なだれ堆積物の層位が浅間白糸テフラとこれらのテフラの間にあるとした新井・矢口(1994)の層序を追認でき、竹本(2008a,b)の層序と矛盾することが明らかになった。浅間総社テフラの上位には砂層などの堆積物がみられ、9,910±70y.BPの放射性炭素年代が得られた。このことから浅間総社テフラと浅間Cテフラの間に見られる水成層は総社砂層に対比されている。
前橋市の元総社西川遺跡(事業団2003)は、染谷川右岸の前橋台地II面に位置している。遺跡では浅間総社テフラの上位に谷を埋めた2層の堆積物が認められ、下位層からは9,910±70y.BPの放射性炭素年代が得られた。また上位の谷を埋めた水成堆積物の上位には浅間Eテフラに対比される可能性があるテフラが認められ、これらの水成層は総社砂層に対比されている。また、菅谷石塚遺跡や元総社西川遺跡では水成堆積物を覆う黒色土から縄文時代中期加曽利E式の遺物包含層が見られることから、これら一連の堆積物の年代が5.0千年前より新しくなる可能性はない。
高崎市の冷水村東遺跡(事業団1998)は、染谷川右岸の前橋台地II面に位置している。遺跡では浅間板鼻黄色テフラの上位に黒色土を挟んで砂礫やシルトなどの水成堆積物が見られる。黒色土からは9,630±60y.BPの放射性炭素年代が得られ、水成堆積物は、総社砂層に対比されている。古環境研究所(1998)は、これらのことから総社砂層の堆積開始年代をこの放射年代に求めた。
前橋市の下東西清水上遺跡(事業団1998)は、八幡川左岸の前橋台地II面に位置している。遺跡では浅間Cテフラの下位に黒色土を挟んで3層準の砂礫からなる堆積物が見られる。黒色土からは下位より6,420±60y.BP、5,190±60y.BP、4,830±60y.BPの放射性炭素年代が得られた。最上位に見られる砂礫層の下位に見られる黒色土には浅間Eテフラと思われるテフラがみられ、黒色土からは縄文時代前期の諸磯C式の遺物包含層が見られる。また砂礫層を覆う黒色土からは加曽利E式の遺物包含層が見られる。これらのことから、この一連の堆積物は、元総社ラハール堆積物を含む総社砂層に対比される。
前橋市の高井桃ノ木遺跡(大友町西通線遺跡調査会1999)及び高井桃ノ木III遺跡(事業団2006)は、八幡川と牛王頭川の中間にある前橋台地II面に位置している。
遺跡では浅間Cテフラの下位に黒色土を挟んで2層準の砂層が見られ、黒色土からは浅間Eテフラ、草津白根熊倉テフラが検出され、上位の砂層の下底に接する黒色土からは4,970±60y.BPの放射性炭素年代が得られた(古環境研究所1999)。黒色土からは諸磯C式、十三菩提式、五領ヶ台式の縄文時代前期後半から中期の遺物包含層が見られ、大友町西通線遺跡調査会(1999)は、これらの堆積物を総社砂層に対比し、新井・矢口(1994)が上位の砂層を元総社ラハール堆積物に想定していると述べた。
前橋市の稲荷塚道東遺跡(事業団2003)は、八幡川右岸の前橋台地II面に位置している。遺跡では浅間総社テフラ、浅間宮前テフラに対比される藤岡テフラの上位に水成堆積物が認められ、総社砂層に対比されている。
前橋市の元総社寺田遺跡(事業団(1996)は、牛池川沿いの前橋台地II面に位置している。遺跡には、浅間板鼻黄色テフラの直下に埋没林が発見され、古環境復元が行われた。また浅間板鼻黄色テフラ、浅間総社テフラ、浅間宮前テフラの上位に砂層が認められ、砂層の上位には浅間D(吉岡)テフラを認めた。
矢口(1996)は、この砂層を総社砂層から分離して元総社ラハール堆積物として定義し、縄文時代前期前半と考えた。しかし、この堆積物の上部ユニットは、模式地周辺の元総社ラハール堆積物に相当する可能性があるが、砂層全体は総社砂層に対比することが妥当であると考えられる。これにより矢口(1996)の元総社ラハール堆積物の呼称は撤回し、今後は総社砂層(早田1990)で統一したい。
元総社寺田遺跡から牛池川の上流に位置する前橋市立元総社北小学校南の露頭は、現在は失われている。新井・矢口(1994)の柱状図C地点にあたり、浅間板鼻黄色テフラ、浅間総社テフラの上位と浅間宮前テフラの間には灰色の火山灰質砂層が認められ、その砂粒は水沢山溶岩によく似ている。これらは水沢山溶岩の噴出に伴うラハール堆積物である可能性が高い。これに対比される砂層は元総社寺田遺跡や柱状図E地点(前橋市問屋町の八幡川沿いの露頭)でも認められ、推定暦年代は13.5千年前である。
前橋市のぬで島川端遺跡(事業団1997)は、利根川左岸の前橋台地II面に位置する。遺跡には、浅間板鼻黄色テフラ、浅間総社テフラの上位に砂層が認められ、総社砂層に対比される。なお、隣接する公田東遺跡の総社砂層中から材が出土し、3,330±110y.BPの放射性炭素年代が得られた(群馬県埋蔵文化財調査センター所蔵資料)。
![]()
![]()
参考文献 Abstract