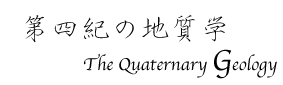 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
|
(8)行幸田岩なだれ堆積物 |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||
(8)行幸田岩なだれ堆積物
カラー
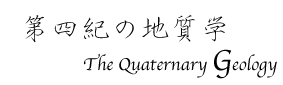
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題
矢口裕之
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月
研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂
大島(1986)は水沢山麓に岩屑なだれ堆積物をみとめ、行幸田泥流堆積物と呼んだ。新井・矢口(1994)は、水沢山溶岩の火砕物を覆う黒色土中に浅間宮前テフラを認め、被覆した黒色土の層位やテフラの年代から行幸田岩なだれ堆積物と水沢山溶岩の年代を9.0〜10.0千年前と考えた。群馬県地質図作成委員会(1999)は、本堆積物を行幸田岩屑なだれ堆積物と呼び、年代に関しては新井・矢口(1994)を踏襲した。
中束(2005)は渋川市の諏訪ノ木V遺跡(事業団2005)で行幸田岩なだれ堆積物の崖錐堆積物を覆う黄色土から縄文時代草創期遺物の出土を報告した。この考古資料の年代は推定暦年代で15.0千年前のものと考えられ、行幸田岩なだれ堆積物の年代と考えたい。
水沢山とその背後にある外輪山には、溶岩円頂丘に沿う馬蹄形の地形が認められる。しかし、水沢山の山麓では、水沢山溶岩に伴う火砕流堆積物や降下軽石などの堆積物は見つかっていない。これらのことからこの地形は地震や火山活動による斜面崩壊で行幸田岩なだれ堆積物を生んだ崩壊地であり、爆裂火口ではなさそうだ。水沢山溶岩がこの凹地に噴出した時期は不明な点が多いが、前橋市の元総社寺田遺跡周辺でこの噴出物起源と思われるラハール堆積物が見つかっている。
(9)徳丸ラハール堆積物
矢口(1999b)及び矢口(2001a)は、前橋市の徳丸仲田遺跡(事業団2001)で浅間板鼻黄色テフラの上位にラハール堆積物を認め、徳丸ラハール堆積物と呼んだ。この堆積物は、浅間板鼻黄色テフラと縄文時代草創期遺物包含層及び浅間総社テフラの間にあることから推定暦年代で15.0千年前と推定される。徳丸仲田遺跡で見つかったラハール堆積物は、層厚30〜200cmの黄灰色〜灰色火山灰質シルト〜粘土層からなり、10〜5cm大の複輝石安山岩質の軽石礫を含んだ火山灰質砂〜砂礫層から構成される。軽石の最大径は30cmに達するものがあり、浅間火山の平原火砕流を起源とする軽石質火山礫が、吾妻川から利根川水系を経て運搬されたものであろう。
同様のラハール堆積物は、前橋市の中内村前遺跡や前田遺跡でも確認できる。そして伊勢崎砂層(新井1971a)にも平原火砕流堆積物の起源の軽石が多く含まれていることから、この堆積物と連続する可能性がある。
徳丸ラハール堆積物は、浅間火山から吾妻川と利根川水系が運搬した堆積物であるが、平原火砕流と浅間板鼻黄色テフラの噴出から1.0千年程度の期間が経過してから堆積したものと思われるが、その成因は明らかでない。
浅間板鼻黄色テフラの上位には、地震が成因となった可能性がある高崎泥流堆積物や行幸田岩なだれ堆積物が見られ、赤城山麓には赤城津久田泥流(竹本2007)と呼ばれる斜面崩壊による堆積物が認められる。
(10)総社砂層
前橋台地の西部に位置する利根川右岸の前橋泥炭層上位には砂層が見られ、早田(1990)はこれを総社砂層と呼んだ。これは、新井(1971a)の水成上部ロームの上半部に相当し、前橋泥流堆積物上の湿地性堆積物と考えられたものにあたる。早田(1990)は前橋台地の模式地の総社砂層は5mを超えるとされ、その層位は浅間総社テフラ降下後の縄文時代早期から前期もしくは後期までに場所ごとに堆積したと考えた。また、その分布は、相馬ヶ原扇状地の一部に見られる新しい扇状地に広がる可能性を示唆し、赤城山南麓の宮川流域の谷を埋めた堆積物も一連の堆積物である可能性を示した。
新井・矢口(1994)は、榛名山麓東南麓から前橋台地に分布する前橋泥炭層上位の砂層を元総社ラハール堆積物と呼び、榛名火山の噴火による堆積物と考えた。またその時代は縄文時代前期から中期にかけての時期とした。日本第四紀学会におけるこの発表には、�「同時期に南関東で同じような現象が各地で見られる。火山活動による地域的なものか検討が必要ではないか�」との意見が寄せられた。矢口(2001a)は、元総社ラハール堆積物の分布が前橋台地の北半部にのみ見られることから、前橋台地を合成扇状地として、前橋岩なだれ堆積物と前橋泥炭層により構成される前橋台地1面と元総社ラハール堆積物により構成される前橋台地2面に区分した。また、元総社ラハール堆積物の層位を浅間E(浅間六合)テフラの上位とし、縄文時代前期末と考えた。
早田(2003)は、新井・矢口(1994)を引用しなかったが、総社砂層の直下に草津白根熊倉テフラを認め、模式地とその周辺に広く認められる総社砂層は、約5000年前頃に堆積を開始したと考えた。また、その要因については榛名火山の大規模な崩壊を認めながらも火山活動のほかに他の地域でも同様の堆積物が認められることを示唆した。
(11)前橋台地層
矢口(2001b)は、前橋台地に分布する表層を構成する砕屑性堆積物を前橋台地層と呼び、浅間Bテフラを境界にシルトや粘土質堆積物からなる下部層と砂質堆積物から構成される上部層に区分した。前橋台地層は、表層土のMb0からMb11まで細分され、テフラや埋没土壌帯を層序に組み込んだ。なお前橋台地層の下位は元総社ラハール堆積物からなる。
![]()
![]()
参考文献 Abstract