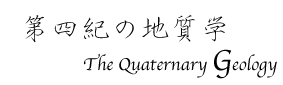 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
|
(5)広瀬川砂礫層 |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||
(5)広瀬川砂礫層
カラー
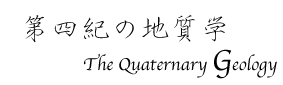
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題
矢口裕之
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月
研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂
新井(1971a)は、広瀬川低地帯の表層を構成し、前橋泥流堆積物より上位にある利根川起源の砂礫層を広瀬川砂礫層と呼んだ。砂礫層の層厚は10m前後と考えられ、その層位は陣場岩なだれ堆積物以降から現在の河床堆積物までと考えることができる。また中世において利根川が現在の流路に移動してからは、桃ノ木川や広瀬川の河成堆積物が表層の砂礫層を構成しているものと思われる。
(6)前橋泥炭層
新井(1962)、新井(1964)は、前橋市の利根川右岸を模式地に上部ローム層下半部が水成堆積し、板鼻褐色浮石層の上下に泥炭から泥炭質粘土を認め、前橋泥炭層と命名した。また新井(1971a)は、前橋泥流堆積物の上位から表土までを水成上部ロームとして中部に見られる泥炭質粘土シルト層を前橋泥炭層と呼んだ。田中ほか(1980)は高崎市綿貫町の群馬の森で地下地質を対象に前橋泥炭層の層序を明らかにした。辻・木越(1992)や辻ほか(1985)は、前橋泥炭層に4層の軽石質火山灰を認め、MB-1、2を浅間板鼻黄色テフラに対比し、MB-3とMB-4を浅間火山起源のテフラとした。
早田(1990)は浅間白糸テフラの上位に砂層を挟んで発達し、浅間板鼻黄色テフラを境に下部の泥炭層と上部の黒泥層に区分した。また早田(2000b)は、本層が浅間大窪沢第1テフラの降灰後に前橋台地の広い範囲で形成されたとしている。
なお、前橋泥炭層の古環境復元は、新井(1962)、田中ほか(1980)、辻ほか(1985)、の花粉分析や中島(1985)の珪藻分析、杉山(1993)の植物珪酸体分析、辻本ほか(1996)の埋没林の古環境復元、林(1994)及び林(1996)の昆虫分析、矢口(2001b)の縄文草創期遺物包含層の分析などがある。
前橋泥炭層とは、高崎泥流堆積物や総社砂層に覆われるまで利根川扇状地で形成された低湿地堆積物である。しかし、黒色で未分解質の植物を含む泥炭の層相を示す層準と分布範囲は限られ、その多くは黒色の泥炭質シルトか黒色泥層である。特に前橋台地の南部地域では本層の発達が悪く、薄い黒色泥層が浅間板鼻黄色テフラ直下に見られることが多い。
典型的な泥炭質堆積物は、現在の利根川沿いに前橋市総社から前橋市六供町までの露頭に多く見られ、浅間板鼻黄色テフラ直下の層準で発見された埋没林は前橋市総社の利根川沿いと前橋市元総社町の元総社寺田遺跡(事業団1996)、前橋市中内町の中内宮前遺跡(2003)などで発見されている。このことは、前橋岩なだれ堆積物堆積後の低湿地は、前橋扇状地に広がっているが泥炭を堆積させるような沼沢地的な環境は元利根川礫層を堆積させた谷沿いに多く見られることを示唆する。
つまり陣場岩なだれ堆積物で埋積され残った一部の谷は開析を受け、低地が形成されて針葉樹林と湿地が広がったのではないかと考えられる。このような場所では、前橋岩なだれ堆積物と陣場岩なだれ堆積物により繰り返された荒廃した環境のなかで比較的に安定した植生環境が提供されたのではないかと思われる。当時の旧石器人類や縄文人がこうした植生をどのように活用したのか、今後は遺跡の発見を含めた検討が必要である。
(7)高崎泥流堆積物
高崎台地(新井・矢口1994)、(群馬県地質図作成員会1999)と呼ばれる高崎市街地が立地する台地や井野川低地帯には時代未詳の泥流堆積物が見られ、田中ほか(1980)は、群馬の森の地下と烏川沿いで前橋岩なだれ堆積物の上位に未詳の泥流堆積物を認めG層と呼んだ。石坂(1985)は高崎市の上並榎南遺跡で軽石流堆積層を認め、本層が普通輝石安山岩質の軽石を含む円礫や流木を含む軽石流であり、層厚は10m以上とした。
早田(1990)は井野川低地帯で元利根川礫層の上位に泥流堆積物を認め井野川泥流堆積物と呼んだ。また、本層は、浅間白糸テフラの上位に層位があると考え、陣場岩屑なだれに対比されると考えた。
新井ほか(1993)は、高崎市街が立地する前橋台地の南西部や井野川低地帯にみられる泥流堆積物は、浅間板鼻黄色テフラの上位にあり、九十九川や増田川の上流に分布が追えることを明らかにし、高崎泥流堆積物と呼んだ。また、その起源は群馬県西部の山地で起こった斜面崩壊によって形成されたと考えた。
早田(2000b)は井野川泥流堆積物を浅間火山起源の小諸第2軽石流堆積物が、大規模な泥流となって烏川沿いに流れくだったと考えた。
中村(2003)は、井野川低地帯に分布する早田(1990)の井野川泥流堆積物が高崎泥流堆積物と同一のものであることを指摘し、またその分布は烏川中流の高崎市上室田町でも認められるとした。このことは高崎泥流堆積物の起源が群馬県西部に広域にあることを意味し、発生要因が榛名山南西麓から秋間丘陵付近で起こった地震であることを示唆した。同様に烏川流域の高崎市中里見原遺跡・中川遺跡でも高崎泥流堆積物が分布することを津島・岩崎(2010)は指摘した。大塚ほか(1997)は烏川中流域で地震による液状化跡を報告し、浅間板鼻黄色テフラの液状化を認めており、地震による高崎泥流堆積物の発生を示唆した。竹本ほか(2008)は、高崎市西部に分布する深谷断層系の活動履歴を目的に採取されたGS-TK1コアの層序を再検討したが、火山活動と深谷断層による履歴や評価は慎重に行う必要があると述べた。
高崎市の上佐野樋越遺跡(事業団2002)の高崎泥流堆積物下の泥炭層からは11,810±70y.BPの放射性炭素年代が得られているという(早田2003)。しかし、このような記述は発掘調査報告書に見当たらない。本層の層位は浅間板鼻黄色テフラの上位にあり、放射性炭素年代及び田中ほか(1980)が示した高崎泥流堆積物直下の冷温帯を示す古植生の年代を勘案すれば、本層の推定暦年代は16.0〜15.5千年前である。
早田(2003)は、井野川泥流堆積物は高崎泥流堆積物に連続する可能性が高いことを指摘し、得られた放射性炭素年代から、高崎泥流堆積物は浅間火山の第2軽石流堆積物に関係した火山泥流堆積物の可能性を示唆した。
しかし、早川(2010)は、浅間火山南麓でみられる第2軽石流堆積物は平原火砕流堆積物から発生したラハール堆積物と考えており、浅間火山軽石流期の大規模噴火について、平原火砕流堆積物1回のみの噴火だったと考えた。また、竹本(2008a)は高崎泥流堆積物に軽石流の堆積様式を示す証拠はなく、早田(2000b)の可能性に対して浅間火山の小諸第2軽石流堆積物は、その分布が烏川上流域の脊梁山地の東側に及ばないことを述べた。
![]()
![]()
参考文献 Abstract