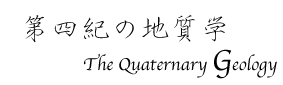|
(3)元利根川礫層
新井(1962)は、北群馬郡吉岡町付近の利根川沿いで泥流堆積物の下位に利根川起源の礫層を認めた。同様の砂礫層は高崎市の井野川河床でも追跡され、早田(1990)はこの利根川起源の礫層上位に浅間白糸テフラを認めて、本層を元利根川段丘堆積物、早田(2000b)は元利根川砂礫層と呼んだ。本層は前橋市の元総社寺田遺跡(事業団1996)の地下10mでボーリング資料によって認められ、陣場岩なだれ堆積物起源のラハール堆積物に覆われている。本層は推定暦年代で23.0〜21.0千年前に堆積し、この礫層は、井関(1983)により最終氷期の最寒冷期に堆積した関東盆地の沖積層基底礫層に比定されている。
本層は、厚さ4m前後の礫層で前橋岩なだれ堆積物が利根川扇状地を覆った以後に下刻した旧利根川により形成された谷を埋めた河成堆積物である。これを竹本(2008b)が復元した谷はやや幅が広い流路である。
過去に発掘された遺跡の資料を参考にしてこの流路を復元した。谷は約2千年間で形成され、その時期は最終氷期最寒冷期にあたる冷涼乾燥気候のもとである。そのため現在よりも降雨量が少なく、河川が形成する谷地形は現在の利根川の流路幅を越えない程度の箱形であったと想像できる。
流路は、前橋市総社、元総社町の元総社寺田遺跡付近を経て、高崎市の日高遺跡と新保田中村前遺跡の間を抜け、高崎市上大類町の井野川と染谷川合流点付近を通過し、井野川低地帯に至っていたと推定される。井野川沿いでやや広めの流路が帯状に形成されたのは当時の榛名火山南麓の水系が井野川に集約されていたためか、高崎泥流堆積物が堆積する以前に烏川が井野川低地帯に流れ込んでいたためかもしれない。
(4)陣場岩なだれ堆積物
新井(1962)は、北群馬郡吉岡町付近の利根川沿いで利根川起源の礫層上位に泥流堆積物を認めた。
森山(1971)は、榛名山南東麓の吉岡町陣場周辺に分布する泥流丘を陣場泥流丘群、その堆積物を陣場泥流堆積物と呼んだ。また、堆積物中に上部と下部のユニットを認め、下部は青灰色の同一岩種の安山岩からなること、また一部に焼けて赤褐色を呈する火砕流堆積物とした。また、上部は下部の堆積物を覆う多種の安山岩礫を含む泥流状の堆積物であることを述べた。
大島(1972)は森山と同様に泥流丘を伴う堆積物は単一種のデイサイト角礫と砕粉から構成され、一部に赤色の高温酸化を認めるも自然残留磁化方位が一定しないなどの特徴を持つことを明らかにした。そして本層は溶岩円頂丘が爆発的に破壊され、水の営力なしに山麓へ移動した堆積物だと考えた。
早田(1990)は、前橋市総社の利根川沿いに前橋岩なだれ堆積物の上位に見られる泥流堆積物を認め、その層位が浅間白糸テフラと浅間板鼻黄色テフラの間にあること、堆積物には岩塊相と基質相の組み合わせが見られることから山体崩壊に伴う岩屑なだれ堆積物に由来していると考えた。この堆積物は、榛名山東麓に分布する陣場岩屑なだれに対比し、その崩壊地は残されていないが相馬山の一部が崩壊したか、崩壊地を相馬山が覆っていると考えた。
新井・矢口(1994)、矢口(1996)は榛名山南東麓で陣場岩なだれ堆積物に伴うラハール堆積物を認め、その層位が浅間白糸テフラと浅間大窪沢1テフラの間にあることを明らかにした。陣場岩なだれ堆積物、相馬山溶岩、陣場岩なだれ堆積物のラハール堆積物の時代は、推定暦年代で20.5〜19.5千年前である。群馬県地質図作成委員会(1999)は、本堆積物を陣場岩屑なだれ堆積物と呼び、年代に関しては新井・矢口(1994)を踏襲した。
竹本(2008a,b)は、榛名山東麓で陣場岩屑なだれの層位が浅間大窪沢1テフラと浅間板鼻黄色テフラの間にあることを示しており、新井・矢口(1994)の層位を修正したが、両者の間に層準の認定に関しては決着を見ていない。
北群馬郡榛東村から吉岡町にかけて建設が進められている県道高崎渋川線高崎渋川バイパスの工事現場では、陣場岩なだれ堆積物の岩塊が露出し、浅間板鼻黄色テフラを挟在する上部ローム層に被覆されていることを確認した。また、このブロックは大きさが10m前後の青灰色安山岩溶岩から構成され、一部に高温酸化が認められ、森山や大島の観察を追認できた。陣場泥流堆積物は、山体崩壊に起源をもつ陣場岩なだれ堆積物と呼ぶのが適当である。
陣場岩なだれ堆積物の起源については、相馬山溶岩円頂丘付近の地形に供給源が考えられること、岩なだれ堆積物中の本質岩塊が相馬山の溶岩に類似すること、岩なだれ堆積物に含まれる多種の安山岩や火砕岩類が榛名山上野平から吾妻山付近の外輪山を構成する火砕物に類似することが明らかである。竹本(2008b)は相馬山と二ッ岳周囲に供給源を示唆するような図を提示した。
水沢山頂から相馬山と二ッ岳周辺の地形観察を行うと広い緩傾斜地と崩壊壁と考えられる崖線が観察される(写真5)。
|
|
|