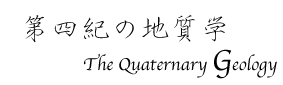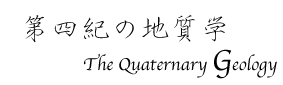 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題
矢口裕之
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月
研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|
|
|
3. 利根川扇状地とその周辺地域の更新統及び完新統の層序
(1)前橋砂礫層
利根川扇状地は、早田(2000b)が呼んだ地形名で高崎台地、前橋台地、伊勢崎台地と井野川低地帯、広瀬川低地帯から構成される。この地形群の最下層は、新井(1971a)、新井(1986)により前橋砂礫層と呼ばれた利根川水系や烏川水系の合成扇状地からなる河成堆積物である。本層の厚さは数百メートルに達すると考えられており、その上流の吾妻川と利根川合流部の河成段丘では、西伊熊礫層(吉田ほか2005)や貝野瀬II礫層(竹本2007)にその一部が対比される。早田(1990)は本層に対比される吾妻川の段丘礫層の頂部に浅間板鼻褐色テフラ群の一部を認めており、それらは後述する前橋岩なだれ堆積物に覆われる。
前橋砂礫層により形成された扇状地は、前橋岩なだれ堆積物に覆われる以前に緩傾斜の扇状地といった景観(早田1990)や広範囲に砂層が堆積する環境を伴い、前橋北部や高崎西部を扇頂として自由に河道を変化させる扇状地の景観(吉田2004a)などが提示されている。また、吉田(2004a)に示された断面図は、現利根川流路に沿って幅2kmほどの緩やかな谷地形が認められる。これは、前橋岩なだれ堆積物に覆われる以前の利根川流路に当たる可能性がある。これについては前橋岩なだれ堆積物中に含まれる火山岩塊の分布について、これを示唆する資料を後述する。
関口(2008)は、前橋砂礫層が形成した扇状地について、前橋岩なだれ堆積物に覆われる以前は、石器石材の獲得場所と狩り場といった旧石器人類の石材及び食糧資源の確保地を想定した。しかし、現在までボーリング資料等で扇状地に当時の離水域を示す風化火山灰土は確認されていない。これは、扇状地に土壌が堆積するような林や草地などの広がりがなかったことを示している。
当時の扇状地に流れる古利根川流路の河道地帯は、大型動物の移動路や秋季のサケ・マス漁を想定した漁労資源地として有効だろう。ただし、扇状地の大部分は氷期の冷涼な気候下で広大な荒廃地が広がっていたものと考えられる。河川礫採取を主目的に荒野の中で遊動することは、当地が食糧採集の点で著しく生産性が低いといった立地性からも少し厳しい条件なのではないだろうか。今後は利根川上流域で河成段丘堆積物の露頭断面での遺跡分布を検討し、前橋扇状地の地形や古環境復元を行う必要があるものと思われる。
(2)前橋岩なだれ堆積物
新井(1967)、新井(1971a)により前橋泥流堆積物と呼ばれた。これは浅間火山の黒斑山が崩壊して形成された岩なだれ堆積物(早川1991a)であり、塚原土石なだれ(早川2010)と総称される堆積物群である。本層に含まれる材の放射性炭素年代は、24,000から21,250y.BPの放射性炭素年代(中村ほか1997)、(下岡2010)を示し、浅間板鼻褐色テフラ群上部に堆積物が流下した層位があることから、推定暦年代は23.5千年前である。
早田(1990)は泥流堆積物中に水で流されたような層理が認められないとし、早田(2000b)は火山岩塊ブロックが前橋市総社付近でも見られることから、前橋台地でも岩屑なだれの様相を残すとしている。早川(2010)は、塚原土石なだれが長野原町応桑で流れ山を残したが、多量の土砂が吾妻川に流入し、利根川を経て前橋で関東平野に達し、河床勾配が緩やかになったため流速が衰え堆積物が残されたとした。
なお、前橋岩なだれ堆積物は、利根川水系に流入した渋川市付近の段丘で堆積物が流れる最中に地表を削剥しながら流下し、流れの接地部に強い剪断応力が生じた(吉田ほか2005)、(吉田ほか2007)との考えと下位層を大きく削剥したり、流走中に衝突破壊した大きなブロックや大量の礫を取り込むような流れではなかった(竹本2007)と考える二者間で論争が起きた。
前橋岩なだれ堆積物中には、火山岩塊の巨大ブロックが含まれることが知られている。中村(2003)は烏川河床で川籠石、聖石、赤石と呼ばれている岩塊を認め、聖石の長径は10m近いと推定した。利根川周辺では、前橋市岩神町の岩神の飛石、敷島町のお艶ヶ岩等が知られている。発掘調査で認められた同様の火山岩塊は、前橋市ぬで島町のぬで島川端遺跡、前橋市鶴光路町の西田遺跡、佐波郡玉村町の福島大島遺跡などで発見された。ぬで島川端遺跡19区で発掘された岩塊は最大径10mの溶岩塊であり、浅間板鼻黄色テフラを挟在する上部ローム層と黒色土に被覆されていることから泥流丘と呼ぶことができる(写真1〜3・群馬県埋蔵文化財調査センター蔵)。
|
|
|
|
 |
|
|
|
写真1 発掘された泥流丘と断面
|
|
|
 |
|
|
|
写真2 発掘された泥流丘の上面
|
|
|
 |
|
|
|
写真3 泥流丘の内部の溶岩ブロック(発泡した火山弾が溶結している)
|
|
| 同様の岩塊は西田遺跡でも検出され、浅間板鼻黄色テフラを挟在する上部ローム層の被覆幅は水平距離で30mに達する西田遺跡の岩塊は、赤色の溶岩塊から構成されるがその大きさは確認できなかった写真4・群馬県埋蔵文化財調査センター蔵)。しかし、岩塊を覆う上部ローム層と黒色土の傾斜が大きいので、岩塊は少なくとも20mに近い大きさであると思われる。 |
|
|
 |
|
|
|
写真4 泥流丘のブロック(写真中央の半月形の褐色部分)
|
|
|
このような岩塊や泥流丘は、現在の利根川や烏川沿いに多く発見されている。これは、他の場所に比べ河川の浸食により露頭条件が良好であると考えることもできる。しかし、利根川沿いの発見例は、河川に関係ない遺跡地下の3例を含んだ5例である。このような巨大岩塊は、岩なだれ堆積物の運搬過程でその場所に堆積したことを考えると、現在の利根川流路の付近には前橋岩なだれ堆積物で埋められた谷地形が存在する可能性が示唆される。つまり、当時の流路が存在した谷を岩なだれ堆積物の先頭部分が岩塊を運び、埋めながら流速を弱めて泥流丘を残したのではないだろうか。
なお、泥流丘が認められた遺跡の他、前橋岩なだれ堆積物の高まりに浅間板鼻黄色テフラ上位の上部ローム層の被覆が認められ例も見られる。このようなことから前橋岩なだれ堆積物の堆積面は泥流丘や浸食による台地上の高まりが存在し、土壌の堆積や植生が認められた可能性が高い。このような景観は、前橋岩なだれ堆積物が流下した後の荒廃地の広がる風景のなかでランドマークになっていただろう。前橋市のぬで島川端遺跡の泥流丘にみられる黒色土からは縄文時代早期撚糸文土器の破片が発見されている。泥流丘が当時の人類の移動生活の拠点となっていた可能性は十分あるだろう。
|
|
|
 |
|
|
 |
|
参考文献 Abstract
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カラー