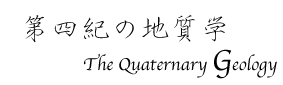 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
|
(4)黒色土層のテフラ |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||
(4)黒色土層のテフラ
カラー
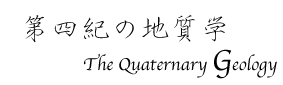
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題
矢口裕之
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月
研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂
浅間宮前テフラ[As-Mm]は、新井・矢口(1994)が榛名火山の水沢山溶岩末端を覆う黒色土に認められた軽石の薄層を呼んだ。このテフラに対比される可能性が高い藤岡軽石[As-Fo]は、かつて命名されたらしいが文献に記載が認められない。早田(1995)は、藤岡軽石は�「藤岡市周辺でよく見かけることができる�」とし、�「藤岡市街地での厚さは、3cm程度である�」とされているが、柱状図は示されていない。本テフラは、浅間起源の鉱物組成を示し黒色土の下半部に層位があることから縄文時代早期の年代が得られた藤岡軽石と同一のテフラであるらしい。
鬼界アカホヤテフラ[K-Ah]は、黒土層に薄層として認められることは希である。遺跡では、黒色土を垂直方向に採取する火山灰分析により、火山ガラスの含有層準として同定されることがある。
浅間六合テフラ[As-E]は、早田(1990)が呼んだ浅間六合[As-Kn]テフラである。竹本・久保(1995)は本テフラの上半部が北北東に分布主軸を持つという。荒牧(1968)の浅間E軽石に対比され、前橋台地周辺では黒色土中に軽石粒や鉱物粒が多く含まれる層準として同定されることがある。
草津白根熊倉aテフラ[Ks-Ku]は、早田ほか(1988)が熊倉a火山灰と呼び、草津白根火山の白根火砕丘を給源とするテフラである。竹本・久保(1995)は、本テフラは白く細粒の岩片からなるという。前橋台地周辺では黒色土中に白色の細粒岩片が多く含まれる層準として同定されることがある。
浅間Dテフラ[As-D]は、新井(1979)が安中市松井田町の千駄木遺跡で検出されたテフラを浅間D降下軽石として命名した。浅間火山起源のテフラ群は荒牧(1968)により浅間火山東麓で記載され、新井はテフラをそれに対比し、その名称を踏襲した。新井(1979)の浅間Dは、荒牧(1968)のD-1軽石に対比した。竹本・久保(1995)は、南東と北東に分布主軸をもつテフラをD2軽石[As-D2]と呼び、荒牧(1968)のD-2軽石との対比を示唆した。なお新井・矢口(1994)は、前橋台地周辺に分布するD-2テフラを吉岡テフラ[Ys]と呼んだ。
浅間C(朝倉)テフラ[As-C]は、山本(1969)が前橋台地で朝倉軽石と命名した。新井(1979)は、荒牧(1968)のC軽石に対比し、浅間C降下軽石[As-C]と呼んだ。早川(2010)は、本テフラには荒牧(1968)の小滝火砕流堆積物が伴うとし、それをC火砕流堆積物と呼んだ。
榛名有馬テフラ[Hr-AA]は、町田ほか(1984)が榛名二ッ岳テフラ群として命名した。降灰分布は榛名山北東麓周辺に限られる。しかし、高崎市の宿横手三波川遺跡では榛名二ッ岳渋川テフラの下位に見られるラハール堆積物には数ミリの角閃石軽石が含まれており、本テフラ起源の堆積物が南麓まで達したことがわかる。
榛名二ッ岳渋川テフラ[Hr-FA]は、新井(1979)が二ッ岳降下火山灰と呼んだ。新井(1962)の沼尾川旧期火砕流堆積物、新井(1979)の二ッ岳第1軽石流堆積物を伴うテフラである。早田(1989)、早田(1993)は本テフラ群を細分し、榛名二ッ岳渋川テフラ[Hr-S]と再定義した。
榛名二ッ岳伊香保テフラ[Hr-FP]は、新井(1962)が二ッ岳浮石と呼び、沼尾川新期火砕流堆積物を伴うとした。新井(1979)は、これを二ッ岳降下軽石として再定義し、沼尾川新期火砕流堆積物は二ッ岳第2軽石流堆積物と呼んだ。早田(1989)や早田(1993)は本テフラ群を細分し、榛名二ッ岳伊香保テフラ[Hr-I]と再定義した。
浅間B(天仁)テフラ[As-B]は、山本(1975)が前橋台地で天仁軽石と呼んだ。新井(1979)は、荒牧(1968)のB軽石に対比し、浅間B降下スコリア・軽石[As-B]と呼んだ。本テフラには追分火砕流堆積物(荒牧1968)が伴う。浅間粕川テフラ[As-Ks]は、新井(1979)の浅間B降下スコリア・軽石の上部を早田(1995)が分離し、命名したテフラである。早川(2010)は、これをB軽石上部と呼んだ。
浅間A(天明)テフラ[As-A]は、山本(1975)が前橋台地で天明軽石と呼んだ。新井(1979)は、荒牧(1968)のA軽石に対比し、浅間A降下軽石[As-A]と呼んだ。本テフラには吾妻火砕流堆積物(荒牧1968)、鎌原熱雲堆積物(早川2010)が伴う。
(5)テフラの命名に関わる問題
テフラは、遺跡以外の調査研究でも対象とされている。その分野は考古学以外に第四紀地質学、地形学、土壌学、地震学、地盤工学など広範囲に及ぶ。このことからテフラには様々な名称や定義が存在し、戦前からの層序研究や戦後の関東ロームの研究などで学史的な名称法が踏襲された。例えばテフラに野外で使用された「ニックネーム」をそのままテフラ名として使用する例など。しかし、広域テフラの発見やテフラのカタログ作りがはじまった1980年代には、定着した様々なテフラの名称と広域的なテフラ編年研究での名称使用とに齟齬が生じ始めた。
このようなテフラ研究の現状について町田・新井(2003)は、テフラの名称はテフラを使う各研究分野の慣習を反映したもので、それぞれ何らかの利点と欠点を含んでいるとしている。また、テフラの名前は給源火山の名称と模式的な分布地の地名を併記した二重命名法を原則とし、旧名を括弧内にとどめておくこと。問題があまりない場合には、すでに記載された名称を尊重することを提唱した。これらはテフラ研究に関する混乱を回避する点で必要な原則だと思われることなどで、なおさら述べることはない。
しかし、今後のテフラ研究において注意する点があるとすれば以下の点ではないだろうか。曖昧な資料でテフラに名称をつけない。必ず模式地の図示及び柱状図を明示する。新たにテフラの名称をつける場合は、隣接地域の地域誌等を含めた文献調査を必ず行う。刊行された報告は別刷を作成し、関係する研究者に積極的に配布する。文献の引用が十分でない地域誌などの著述にあたっては、新たなテフラの定義は避ける。発掘調査報告書を引用する場合は、必ず記載を確認して引用する。必ず原典を複写するなどして記載事実を確認し文献の孫引きはしないこと。などであり研究以前の常識的な事柄が多く含まれている。
![]()
![]()
参考文献 Abstract