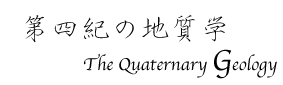 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
|
(2)中部ローム層のテフラ |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||
(2)中部ローム層のテフラ
カラー
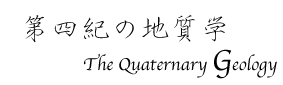
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題
矢口裕之
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月
研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂
榛名八崎テフラ[Hr-HP]は、原田(1943)の赤城南台浮石の分布を訂正し、新井(1962)が定義(新称)した。本テフラは、榛名火山の山頂カルデラを給源とし白川火砕流堆積物(新井1962)、榛名軽石流堆積物(森山1971)室田軽石流(大島1986)を伴うテフラである。前橋市の富田下大日遺跡では、軽石質火山礫からなるテフラの上位に火山灰層が認められ、白川火砕流堆積物のサーマルから発生した降下火山灰であると考えられる。
赤城鹿沼テフラ[Ak-KP]は、新井(1962)が呼んだ赤城火山の山頂カルデラから噴出した大規模なプリニー式軽石である。火山の東麓から太平洋岸まで広く分布し、「鹿沼土」の名前で知られている。噴出量の規模が大きい割に火砕流などの堆積物は伴わない。
榛名御陰テフラ[Hr-Mg]は、新井・矢口(1994)が呼んだ榛名八崎テフラと榛名中郷テフラ間にみられるスコリア質火山礫の薄層である。榛名東麓にのみ確認され、竹本(2008b)は同様の榛名火山起源の火山礫層を複数枚認め、本テフラを御陰火山礫層-1と呼んだ。
榛名三原田テフラ[HMP]は、竹本(1985)が三原田軽石と呼んだ。その後に早田(1989)は榛名八崎火山灰[HA]、新井(1989)は八崎火山灰[HA]、新井・矢口(1994)は榛名中郷テフラ[Hr-Ng]、早川(1995b)の榛名勝保沢テフラ、早田(1996)は榛名箱田テフラ[Hr-HA]と呼んだ。本テフラは榛名火山を起源とするテフラで白川火砕流の一部の火砕流堆積物を伴うらしく、カミントン閃石が含まれるといった特徴がある。これは竹本(2008b)の荒巻火砕流にあたる。
大石・下司(2009)は白川火砕流堆積物に含まれる斜長石の屈折率の傾向から火砕流は3種類に区分され、そのうちの2種類は榛名八崎テフラと榛名三原田テフラに対応することを明らかにした。
早田(2010)は、榛名箱田テフラの出典を早田(1996)に求め、八崎火山灰(新井1989)の名称使用は好ましくないと述べた。しかし、早田(1996)にはテフラの模式地や柱状図の記載及び新井(1989)の榛名八崎火山灰への対比や引用がなく、また竹本(1985)も引用していない。このような点から三原田テフラにつけられた個々の地域的なテフラ名は、その研究史的価値を認めることができる。しかし、榛名箱田テフラの名称の使用については納得しがたい。
(3)上部ローム層のテフラ
姶良Tnテフラ[AT]は、町田・新井(1976)により発見され、上部ローム層の下底にみられる広域テフラである。県内では火山ガラスからなる細粒火山灰の層相を呈し、遺跡では火山灰土を垂直方向に採取する火山灰分析で、火山ガラスの含有層準として同定されることがある。
浅間室田テフラ[As-MP]は、新井(1962)が呼んだ板鼻褐色浮石の一部を分布や層相の違いから森山(1971)が分離(新称)した。
早田(2010)は、浅間室田テフラの使用について、後述の浅間板鼻褐色テフラ群から分離して記載する根拠が十分でなく、室田テフラの使用が無用な混乱を招くとした。しかし、早田(1995)では、図10に浅間山テフラの堆積状況を示し、板鼻褐色軽石群の最下層に室田軽石を示した。また文中で�「最も下位にある軽石は、特に規模が大きく層相も特徴的で、As-BP Group自体が元より異なる噴火に由来するテフラの集合であることも考慮して�「室田軽石(MP、森山、1971)�」と特別に呼ばれることがある。�」としている。
このようなことから、現在ではその特徴的な層相で野外での識別が容易である浅間室田テフラについて、何が不都合なのか理解に苦しむところである。
なお、早田(2010)では、町田・新井(2003)に記載されている、浅間板鼻褐色テフラ(群)の最下部が浅間室田テフラで、下部、中部、上部の軽石の火山ガラスの記載に関する層序について以下のとおり記述した。�「下部と上部の境界は、MPを構成するフォール・ユニット間に存在することがわかってきた。�」これが事実であれば、町田・新井(2003)が示した浅間板鼻褐色テフラ群のユニットの層序関係は、矛盾していることになる。またそのテフラの定義に掛かる問題ではなかろうか。どのような事実や調査資料に基づいて、何がわかってきたのかを丁寧に記述しなければ、それこそが無用な混乱をきたす恐れがあるものと危惧している。
浅間板鼻褐色テフラ群[As-BP]は、新井(1962)により板鼻褐色浮石と呼ばれた。テフラ間には火山灰土が挟在し、時間間隙を伴う複数のテフラから構成される。新井(1962)では2層準、町田ほか(1984)では3層準に区分した。なお、町田・新井(2003)では、最下部に浅間室田テフラを含み浅間板鼻褐色テフラ群としているので、室田テフラの呼称との併用には注意が必要である。
浅間白糸テフラ[As-SP]は、新井(1962)が呼んだ板鼻褐色浮石の一部とされ、町田ほか(1984)が定義(新称)した。しかしその分布は、新井(1962)の板鼻黄色浮石の分布範囲に含まれていた可能性が極めて高い。
浅間大窪沢テフラ1、2[As-Okp1,As-Okp2]は、中沢ほか(1984)、中沢(1989)により命名された。上部ローム層中の浅間白糸テフラと浅間板鼻黄色テフラの間に薄層としてみられ青灰色の岩片が特徴的に含まれる。
浅間板鼻黄色テフラ[As-YP]は、新井(1962)により板鼻黄色浮石と呼び、第1軽石流堆積物(荒牧1968)、平原火砕流堆積物(早川2010)を伴うテフラである。同時期の噴出物である浅間草津テフラ[As-K]と上位に火山灰互層が見られる。これらの火山灰の一部は広域に分布し[UG]と呼ばれる。
浅間総社テフラ[As-Sj]は、辻ほか(1985)が前橋台地でMB-3と呼び、パリノ・サーヴェイ株式会社(1990)が命名した。前橋台地周辺では上部ローム層最上部の黒色土との漸移帯に見られる。
![]()
![]()
参考文献 Abstract