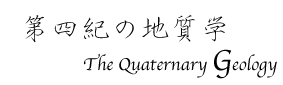|
2. 火山灰土とテフラ層序の問題
関東平野北西部に分布する火山灰土は、岩宿遺跡の発見により認識され、層序区分が行われた(杉原1956)。それらは下位より金毘羅山角礫質粘土層、岩宿暗褐色粘土層、阿左見黄褐色細粒砂層からなる関東ローム層と笠懸腐食表土層からなる。関東平野北西部の利根川流域に分布する後期更新世から完新世の火山灰土の層序は、久保・新井(1955)や新井(1956)が明らかにし、関東ローム層の一部である下部ローム層、中部ローム層、上部ローム層(新井1962)と黒土層(新井1979)に区分された。
(1)中部ローム層と上部ローム層の層序区分
新井(1962)は、上部ローム層と中部ローム層の境界を板鼻褐色浮石層の下位に普遍的にみられる暗色帯上面におき、その岩相的特徴が上部ローム層は複輝石安山岩質であり、中部ローム層は角閃石に富むことを上げた。その後、町田・新井(1976)は、赤城火山南麓で広域テフラの姶良Tnテフラの対比を行い、その降下層準を中部ローム層最上位の暗色帯上部においた
森山(1971)は、板鼻褐色浮石層の下位にクラック帯を認め、クラック帯上面を上部ローム層と中部ローム層の境界とした。またクラック帯の下位にみられるテフラを室田浮石層と命名し中部ローム層に含めた。
上杉ほか(1983)は、室田軽石下位の黒色帯上面に上部ローム層と中部ローム層の境界を認めた。また中部ローム層最上部のAT層準の下位に斜交層準を認め、中部ローム層最上部の黒色帯の下限と推定した。
矢口(1999a)は、群馬県北西部のローム層の層序区分を行い、浅間板鼻褐色軽石層、浅間室田軽石層、姶良Tn火山灰層を上部ローム層に含め、AT層準下位の風化帯上面を上部ローム層と中部ローム層の境界とした。またその岩相的特徴に上部ローム層は複輝石安山岩質であること、中部ローム層は角閃石安山岩質であることをあげた。
関口(2008)は、大間々扇状地桐原面の大上遺跡のローム層の区分を行い、As-BP Groupを挟在する黄褐色ローム層の5層、As-MP、ATを挟在する褐色ローム層の6層、灰黄褐色軟質ローム層の7層、暗褐色軟質ローム層(暗色帯)の8層に区分した。関口の層序区分は、中部ローム層から上部ローム層において、更なる細分化を進めたが、従前の関東ローム層の層序区分方法を踏襲しなかったことは残念である。
県内の関東ローム層は、新井(1962)、関東ローム研究グループ(1965)や新井(1971b)により層序区分が行われた。関東ローム層の起源は、火山灰土の堆積物としての供給源を一次的な火山噴出物に求めた。また火山活動の休止期を示す暗色帯〜亀裂帯(クラック帯)や不整合関係を重視して、火山灰土と地形面の被覆関係を考慮に入れて層序区分がなされた。新井(1962)は、上部ローム層中の浮石層と火山灰土の層厚を明らかにし、浮石層が給源から離れるにつれ層厚を変化させるのに対し、火山灰質な細粒部は層厚に変化がないことを明らかにした。
ところが中村(1970)や早川(1991b)、早川(1995a)は、ローム層が火山からの一次的な噴出物ではなく、火山周辺に堆積した火山噴出物を起源とする風塵であると述べた。また火山灰土は、火山の休止期に関係なく一定の速度で堆積することを明らかにした。鈴木・早川(1990)は、県内のテフラの年代をこうした観点で論じ、矢口(1999)もこのような考え方を追認した。しかし、このような事情で近年は関東ローム研究グループが提唱した火山灰土を火山の休止期で区分する層序区分方法の前提が覆り、火山灰土そのものの層序に関する研究が著しく減少した。早田(1990)や竹本・久保(1995)のテフラ研究では関東ローム層の区分に関する論述が消えた。
ところで旧石器時代の遺跡発掘では、火山灰土を地層として層相や岩相により区分し、暗色帯などの土壌帯を重視して遺物包含層を文化層と呼んで認識する方法論がすでに一般化している。つまり旧石器研究において文化層の対比や遺跡群の編年、形成論を論じる上で火山灰土の層序区分と対比に関する研究は不可欠であると思われる。また火山灰土は火山噴出物が二次的な堆積作用で形成された広域風成塵堆積物であり、黒色帯と呼ばれる埋没土壌は氷期の温暖期に形成された腐食土である可能性が高い。このような点からも火山灰土の層序区分に関する研究は、今後も旧石器時代の古環境復元や古地形を理解する上でも欠かせないものと思われる。
|