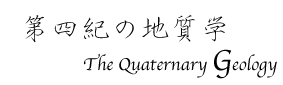 |
関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題 矢口裕之 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団発行 2011年3月 研究紀要 第29号 21-40頁から転載をWeb版として改訂 |
|||||
| 1. はじめに 関東平野北西部の利根川流域は、関東山地や足尾山地の古期岩類からなる山塊とその周縁に分布する新第三系の丘陵及び中期から後期更新世の火山活動で形成された火山に囲まれている。新生界の地層群は中古生界からなる古期岩類に対して、地溝状もしくは盆状の構造を呈している。かつて新井(1965)は、この地域に第三紀末の火山構造性陥没を提唱し、この構造運動を関東造盆地と切り離して考えた。野村(1977)は、盆状の地質構造を内陸盆地の一部として捉え、これを前橋堆積盆地と呼んだ。 新井(1962)、関東ローム研究グループ(1965)や新井(1968)は、関東平野北西部の第四系の層序学的研究を行い、利根川流域で初めて包括的な第四系の編年を確立した。また早田(1990)、早田(2000b)、早田(2008)は、この地域の地形発達史と第四系の編年を行い、利根川流域の地形群を利根川扇状地と呼称した。竹本(2008b)は、利根川中流から上流域の段丘を中心に火山性コントロール地形発達史の観点から関東平野北西部の第四系の編年をまとめた。 関東平野北西部の第四紀研究は、関東ロームの総合研究以後に著しい進展をとげた。これらの研究は、人口密度の高い都市部や海岸地域を対象とした南関東地域の研究水準と遜色ないものであった。それは、この地域で日本列島に初めて旧石器文化の存在が認められ、関東ローム層の研究と相まって編年研究が進んだこと(相沢1957)である。また、火山とその噴出物の層序が解明されたこと、例えば守屋(1968)、荒牧(1968)、早川(1983)、大島(1986)、守屋(1986)、鈴木(1991)、鈴木(2000)、早田(2000a)などが挙げられる。 新井(1979)による縄文時代以降の指標テフラや竹本・久保(1995)の総括的なテフラ研究は、この地域の第四系を火山灰層序学により高精度の編年網で括ることに成功した。テフラの年代測定に関する研究は、1960年代より浅間火山の噴出物を中心に進められ、中村ほか(1997)や辻ほか(2004)により総括されている。 群馬県内の発掘調査は1970年代に入り急増し、大型幹線道路の建設を皮切りに公共幹線を中心とした大規模な調査が2000年代まで続いた。この間に調査された旧石器時代から縄文時代の遺跡は、膨大な数に及ぶ。しかし、調査で得られた自然科学的な資料は、調査報告書に掲載されるが、その活用や集成は進んでいない。最近行われた岩宿フォーラム2008では、遺跡群の形成と地形発達に関する討論がなされた。 本論文では、新井(1962)にはじまる関東平野北西部、特に前橋堆積盆地の上部更新統から完新統について概要を述べその問題点を議論する。また、この地域の遺跡と第四系に関わる問題について論じた。 |
||||||
| 参考文献 Abstract |
||||||